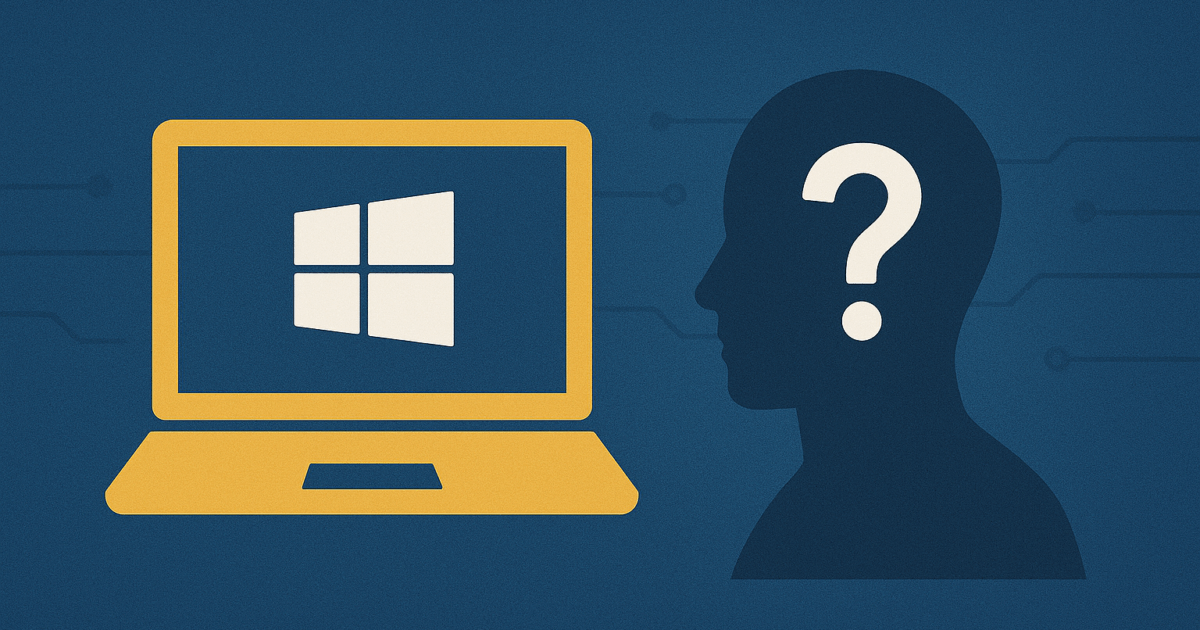2025年10月にサポート終了が予定されていた Windows 10 ですが、マイクロソフトは 有償オプション ESU(Extended Security Updates) を発表し、 最大2028年まで延長可能であることを正式にアナウンスしました。
本記事では、個人事業主や中小企業が取るべき対応を、ITインフラの観点から解説します。
Windows 10 延長の背景
- 利用者の規模:数億台が依然として稼働中
- システム互換性:業務アプリや周辺機器のWindows 11未対応が多数
- コスト負担:PC買い替えやOS移行に伴う投資が重い
このような現状を踏まえ、延長は現場のニーズに応えた「時間稼ぎ策」といえるでしょう。
ESUの内容と注意点
ESUで提供されるのは セキュリティ更新のみ です。新機能や改善は受けられません。
また、ライセンス料は年間課金制で、PC台数が増えるほどコストが膨らみます。
リスク面
- 脆弱性対策は行われるが、新機能は追加されない
- 最新ハードウェアやソフトとの互換性ギャップが広がる
- 長期的にはWindows 11移行を避けられない
専門家視点での移行チェックポイント
1. ハードウェア要件の確認
Windows 11は「TPM 2.0」や「Secure Boot」など厳格な要件を求めます。
自社PCが対応しているかをまずチェックしましょう。
2. ネットワーク機器・VPN環境
YAMAHA RTXシリーズやUTM機器を利用している場合、
Windows 11でのVPNクライアント動作検証が不可欠です。
特に IKEv2やL2TP/IPsecの認証方式 は動作差異が出やすいため要注意です。
3. 周辺機器・業務アプリの互換性
NAS、プリンタ、IPカメラなどの業務周辺機器がWindows 11に対応しているかを確認しましょう。
古いドライバは未対応のケースが多く、OS移行後に業務が止まるリスクがあります。
4. セキュリティ運用の再設計
Windows 11では「標準での強化セキュリティ(Defender強化、ハードウェア隔離)」が進んでいます。
移行に合わせて社内のセキュリティポリシーやログ管理を見直すことを推奨します。
まとめ:延長は猶予、移行は必須
Windows 10 延長(ESU)は朗報ですが、あくまで「移行までの猶予期間」です。
個人事業主や中小企業は今のうちから 計画的な移行シナリオ を描き、
ハード・ソフト・ネットワーク全体の検証を進めることが、長期的な安定運用につながります。
※当サイト(新神戸ITサービス)では、Windows 11移行支援、ネットワーク機器の互換性確認などのご相談も承っております。